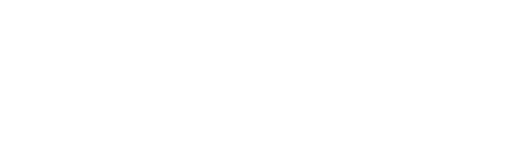坂本一太さま
(横浜市)

目標に向かって集中して取り組む力が、現実世界でも役に立つんだろうと思います。
- 横浜つみきへ通う前、「つみき」に対してどんなイメージを持っていましたか
- 直方体とか立方体の形を積み上げて遊ぶ!ってイメージですね。写真に良く出てくるような積み木のお城を作ったり…と言うイメージですね。
- 「積み木遊び」を子育てに取り入れようと思ったきっかけはなんですか?
- 妻の子育ての意識というか、教育手法についてものすごく熱心に研究しているので、そこで「やろう」となったことがきっかけですね。
- 横浜つみきを知ったきっかけは?
- それも妻がいろいろとネットやツイッター(X)とかSNSとかでいろいろ調べてまして、「ここへ行きたい!」と言うことで、通い始めました。
- 毎回パパがお子様を連れてご参加されていますね。
- はい、まだ下の子が8ヶ月ということもあるんですけど、多分、どっちかというと妻は積み木のような3次元の遊びが多分苦手なんじゃないかなと思うんです(笑)
- なぜ、横浜つみきに行ってみようと思われましたか?
- やはり自宅ではそこまでたくさんの積み木を揃えるのは難しいんですよね。それで、ここは本当にたくさんの積み木があって、種類も豊富だし、量や質もしっかり揃っている場所だと聞いて、是非行ってみたいと思いました。
- ご自宅には積み木はお持ちですか?
- 少しだけあります。確か、立方体と直方体が混ざっているものが1箱かな。
- 実際に横浜つみきで遊んで、親御さん自身がつみきや童具のことをどう思いましたか?
- 一番感じたのは、木の素材の良さがとてもよく表れているということです。他の場所で見かける積み木だと、色が塗られていたりして見た目重視な印象があるんですけど、横浜つみきさんで扱っている積み木は素材そのものの魅力を大切にしていると感じました。
- お子様は教室で遊んでいるときや遊び終わった後、どんな様子ですか?また、どんなお話をしてくれますか?
- 正直ものすごく集中して遊んでいるので、終わった後は毎回かなり疲れている様子ですね。お昼ご飯を食べるとすぐに寝てしまうくらいです。それだけ頭を使って真剣に遊んでいるんだろうなと感じます。また、教室ではお友達や年上のお兄ちゃん・お姉ちゃんたちとも関わりながら遊んでいて、例えば「どうぞ」と声をかけてもらうなど、交流を通じて成長している姿が見られるのも嬉しいですね。
- 横浜つみきに通ってみて、親御さん自身、先生たちのことをどう思いましたか?
- いつも子どもたちのことをよく見てくださっているなと感じています。それぞれの興味や関心に気づいて、それに合った形で導いてくれるところが本当にありがたいです。親としても信頼してお任せできる先生方だなと思っています。
- 横浜つみきの特徴やサービスなども含め、どんな所を気に入っていただいていますか?
- スケジュールを柔軟に決められるところがとてもいいと思っています。それに、大人も一緒に遊べる環境があるのが魅力的ですね。私自身、普段あまり使わない頭を使うので、それが新鮮でとても楽しいです。一緒に遊ぶ中で、子どもだけでなく自分も良い刺激を受けられるのが気に入っています。
- 30年後を想像してみてください。お子様はどのような大人になっていますか?浮かぶ風景をありのままに話してみてください。
- そうですね。私自身、72歳になっていると思いますが、子どもはその時32歳ですね。どんな大人になっているのかを想像するのは少し難しいですが、願いとしては、自分で考え、主体的に物事に取り組む人になっていてほしいと思っています。地域や環境にとらわれず、広い視野を持って、自分の力で道を切り開いていけるような、そんな大人になっていてくれたら嬉しいですね。
- お子様には将来どんな大人になってもらいたいですか?どのような生き方をしてほしいですか?
- 何だろう…そうですね、経営者になってほしいですかね。
- お子様には経営する側、自分で生み出す側になってほしいと仰っていましたが、最終的にお子様にどんな生き方や信念を持ってほしいなど、何か思い描くイメージがありますか?
- さっきの話にもつながるんですが、やっぱり「夢中になる力」が大事だと思っています。夢中になる、もしくは夢中になれることが、人が成長するための原動力だと思うんです。自分で「こうありたい」というビジョンを持ち、それに向かって進む力ですね。例えば、積み木遊びでも、私自身、何か作りたいなと思って考えるんですが、明確に完成形をイメージするのは難しいと感じます。一方で、子どもの頃に模型を作ったときのことを思い出すと、パッケージに描かれた完成形を見て「これを作りたい!」と明確に思えたんですよね。その目標に向かって集中して取り組む力が、現実世界でも役に立つんだろうと思います。そうした力をどうやって日々の生活や教育で身につけてもらうか、私自身も意識しながら子育てをしています。その力が将来、どんな分野でも活かせる原動力になると信じています。
- お子様との時間で何か大切にしていること、必ずこうしようと決めていること、何かありますか?
- そうですね、例えば子どもが「かくれんぼしたい!」と言ってきた時は、疲れる時もありますけど、なるべく付き合うようにしています。やっぱり一緒に過ごす時間は大切ですから。それと、褒めることを意識しています。昨日も妻と話していたんですが、自己肯定感を育むには、やっぱり小さい頃から「誰かに愛されている」「認められている」と感じる経験が必要だと思うんです。否定するのではなく、たとえ失敗することがあっても、安全な範囲なら挑戦させてみる。そうやって子どもが自分に自信を持てるような環境を作っていきたいと思っています。
- 子育てをしていて、難しい、困った、うまくいかない、と悩むことはありますか?「はい」の場合、具体的にどんな時にそう思いますか?
- 日々悩んでいますね。今まさに「いやいや期」の絶頂期で、何かやりたいけどできないと怒ったり、寝転がったりと大変な時期です。例えば、最近までは歯磨きをすごく嫌がって困っていたんですが、ほんの数週間前から急にちゃんとやるようになったんです。その理由を考えてみたんですが、「褒める」ことが大きかったのかなと思います。例えば、「歯磨きが上手にできるところを見せて!」とか、「本当に上手にできるの?」とちょっとした挑戦のような形で声をかけると、やる気を出してくれるんです。
子育てって、ずっと試行錯誤の連続ですよね。人類が誕生してからずっと続いているのに、完成形がないというのが面白いなと思います。それこそ、そういった試行錯誤や多様性が、人類が今まで続いてきた力の源になっているのかなと感じますね。
でも本当に大変なことも多いです(笑)特に言葉を使って自分の思いを必死に伝えようとしている子どもの姿を見ると、「この子も一生懸命なんだな」と思わされます。 - 普段お子様はご自宅や園でどんな遊びをして過ごすことが多いですか?また、好きですか?
- うちの子はまだ園には通っていないのですが、月に2~3回程度の一時保育には行っています。その中で絵の具を使ったり、水遊びをしたりすることがあるようです。こういった遊びは家ではなかなかできないので、保育園で体験できるのは貴重だと思っています。家では、こういった活動はちょっとハードルが高くてやらないんですが、園での遊びはそれとは違った面白さがあるようですね。ただ園に通う頻度が少ないので、特別な遊びがなかなかできないという部分もありますが、そんな中でも園での生活は大切な経験だと思っています。
自宅では、平日も休日も、子どもと一緒に遊ぶ時間をできるだけ作るようにしています。最近は家で絵本を読んだり、かくれんぼをよくしています。ただ、かくれんぼは本当に「永遠ループ」で(笑)、結構疲れるんですけど、頑張って付き合っています。
外では、公園に行ったりすることが多いですね。休日になると少し遠出して、博物館や他の公共の施設に行くこともあります。特に最近は夏の暑さで外遊びが難しいので、屋内の施設を活用することが増えました。
本当にいろんなことをして、子どもと笑顔で過ごす時間を大切にしています。公園で一緒に遊んだり、何かに付き合ってあげる時間が、親子のいい思い出になっているなと感じます。 - 現代は様々な教育法や習い事が存在しますが、そんな中なぜ「積み木」という玩具に対して重要性を感じましたか?
- 一番の理由は、積み木が主体性を育む点だと思っています。自分でイメージを描いて、それを形にする過程が大切で、その経験を通じて主体的に物事を考える力が養われると感じます。モンテッソーリ教育法にも共感しており、この方法はとても良いと考えています。それを家庭でも取り入れたいと思い、積み木を使って、自分で考えて作る力を育む方法を実践しようとしています。
- 積み木は本来こどもから大人まで誰にとっても楽しめる遊びです。ところが、積み木に全くなじめず、楽しめない方もいます。それはなぜだと思いますか?
- 完成形がイメージできないことが原因じゃないかな、と思います。写真を見て「これを作りたい」と思えれば、夢中になれる人が多いと思うんですが、何を作りたいのかが分からないと楽しめないと思います。私もその完成形をイメージするのが難しくて。だから、絵を描く芸術家などがすごい才能を持っていると思うんですよね。まだ誰も見たことのない完成形を自分の頭の中で作り出すわけですから、それはすごいことだと思っています。自分にもそういった能力があればいいなと思いますね。
- 先ほどモンテッソーリが出てきましたが、坂本さまが思う、理想的な子育てや教育とはなんですか?また、その実現は簡単ですか、難しいですか?
- 難しい質問ですね。理想的な教育というものは一概に決められないと思います。やっぱり、子どもの成長過程や教育環境によって、必要なアプローチは変わってきますから。親がこういう教育方針を持っていても、それが必ずしもその子に合うとは限りません。そこが難しいところです。ですから、子ども一人ひとりの成長に合わせて、教育方針を柔軟に考えていく必要がありますね。大事なのは、親が作り上げるのではなく、子ども自身がその過程で成長できるように見守ることだと思います。
教育においては、完成された状態だけを目指すのではなく、子どもが自分で「何を作るか」を考え、実際に作るという過程を重視することが大切です。その過程で自分で学び、遊びながら成長していけることが理想的だと感じています。 - 積み木の難しい所は、初めから楽しいものやすぐに遊べる状態に完成されておらず、「自分たちでまず作ってから遊ぶ。何を作るか?も考える」という過程が必要です。この少し大変だったり手間だったりする高度な遊びを取り入れて育つと、大人になった時に、どんなことに役立ちそうですか? また、大人自身もこの環境で遊ぶことでどんないいことがありそうですか?
- それはもう、社会人として必要最低限のスキルだと思います。限界に挑戦する力、問題解決能力、創造力が身に付くということです。子どももこうした環境で遊んでいると、きっと良いことがあると思います。私個人としては、積み木を使うことで、頭を使うというのが新鮮です。特に育児をしていると、黙々と2時間も単純作業をすることって少ないので、そういう意味で脳の使い方がちょっと新しい感覚になります。手を動かしているうちに、思いがけない斬新な発想が出てくることもあって、たまにですが、それが面白いですね。
- これから横浜つみきに遊びに来てみたいと思っている方へ一言お願いいたします。
- やっぱり安全な環境で、たくさんの種類の積み木が揃っていて、それにとても詳しい先生がいらっしゃいます。そして、過去の具体的な事例を見ながら、積み木遊びに没頭できる環境が整っています。とても充実した時間を過ごせると思いますよ。