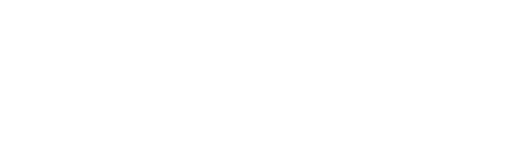堀江茉依子さま
(静岡県)
「これはお教室に行かなきゃできない、非常に価値のある遊びだ」と本当に思いました。
- 横浜つみきへ通う前、「つみき」に対してどんなイメージを持っていましたか?
- 積み木は小さい子どもがやるものだと思っていました。具体的には7歳くらいの子どもが使うものだと思っていて、幼稚園とかで積んだりする場面を見たことがあったので、その後は赤ちゃんと始めて、少しずつ発展して高い家を作ったりして、最終的にはレゴなどに移行するんだろうなと思っていました。つまり、積み木は幼児期を過ぎると卒業して、何か別のものに興味が移るというイメージでした。
- 「積み木遊び」を子育てに取り入れようと思ったきっかけはなんですか?
- 積み木が「いい」って言われてるからですね。それが一番最初のきっかけです。息子が何歳の頃だったかちょっと覚えていませんが、当時家には積み木がすでにありました。息子が積み木を使えるようになったのは1歳を過ぎたくらいの頃だったと思います。なので、家に積み木があること自体は特別なことではなく、積み木遊びがすでに子育ての一部というイメージでした。ただ、特に「積み木遊び」というものを生活の中で特別に意識することはなかったですね。
- 横浜つみきを知ったきっかけはなんですか?
- 色々インターネットやSNSで調べている中で、まず童具館のホームページにたどり着きました。けれど、それが東京にあったので、通うにはちょっと遠いなと思い、もっと近くにないかといろいろ探していたところ、さつき先生のお教室を見つけました。
- なぜ、横浜つみきに行ってみようと思われましたか?
- 自宅にいろいろな積み木を揃えようと思って、購入を検討していたのですが、価格が高かったり、全部を揃えるにはどれくらいの量が必要なのかがわからなかったり、さらにこの子がどれくらいの期間遊ぶかということを考えると、ちょっと躊躇してしまいました。そんな中で、もっと気軽に積み木に触れ合える場所、自然に積み木と触れ合える環境はないかと探していたところ、横浜つみきを見つけました。
- 実際に横浜つみきで遊んで、親御さん自身が積み木や童具のことをどう思いましたか?
- 最初に遊んでみて、「これはお教室に行かなきゃできない、非常に価値のある遊びだ」と本当に思いました。こういう積み木遊びを今まで見たこともなかったですし、経験したこともなかったので、驚きでした。積み木を使って、ゼロから無限の発想を生み出せるということに気づきました。「積み木ってこんなことができるんだ」「こんな風に考えて、できるんだ」と、目から鱗でした。何でも自由にやっていいという、そういう遊ぶ環境に感動しました。
- お子様は教室で遊んでいるときや遊び終わった後、どんな様子ですか?また、どんなお話をしてくれますか?
- 「また行きたい!」っていうのはすぐに言っていましたね。定期的に「石川町だ、石川町だ」と言って、行くのを楽しみにしています。道のり自体も楽しんでいて、教室に行くことをすごく楽しみにしているみたいです。お家に帰ってからは、どんなお話をしてくれるかワクワクしますね。たとえば、「今日何を作ったの?」と聞くと、「これを作った!」と言って、「これと、これと、これを作ったんだよ」と作ったものを教えてくれます。また、私や夫にその日作った作品の写真や動画を見せて、家族みんなで「すごいね!」と喜んでいます。
- 横浜つみきに通ってみて、親御さん自身、先生たちのことをどう思いましたか?
- すごく驚いたのは、息子がこの1年間でやった何気ない行動を先生方がちゃんと覚えていて拾ってくださったり、ちょっとしたところでも息子の良いところを見つけて褒めてくださることです。あとは、息子がこうしたらいいんじゃないか?と考えたことを、先生が具体的に形に出来る様に導いてくださるところもありがたいです。また、先生方から「こういう見方もあるんだ」とか、「この息子の行動はこう解釈できるんだ」という新しい視点を教えていただき、私自身もとても勉強になる場面が多いです。
- 横浜つみきの特徴やサービスなども含め、どんな所を気に入っていただいていますか?
- はい、まさにそこが一番気に入っています。例えば、みんなで遊ぶことができるし、下の子も一緒に連れてきても大丈夫ですし、私が「ちょっと集中してほしいな」と思うときには、子どもを貸切対応で預かってもらえますし、本人が積み木に集中できる環境が整っているところがとてもありがたいです。状況に応じて柔軟に対応していただける点が本当に助かっています。
- 30年後を想像してみてください。お子様はどのような大人になっていますか?浮かぶ風景をありのままに話してみて下さい。
- 実はずっと考えているんですけど、まだわからないなって思っています(笑)でも、子どもが30代になっている頃、周りの家族が口を揃えて言うのは「今のままで大きくなってほしい」ということです。反抗期があっても、今の優しさや性格が薄れることなく、そのまま大人になってほしいとみんなが願っています。わたしの母もよく「賢くて優しいけんちゃん」と言ってくれていて、会うたびにそんな風に言ってくれているんです。
- お子様には将来どんな大人になってもらいたいですか?どのような生き方をしてほしいですか?
- これも主人と話し合ったんですが、名前に込めた意味に通じる部分があります。名前の通り、感謝の気持ちを忘れず、他の人を敬い、謙虚な心を持ち続けてほしいと思っています。
- 普段お子様と何をして遊んだり過ごすことが多いですか?平日と休日に分けて教えて下さい。
- 平日は下の子がいるので忙しくて、上は年長なので幼稚園が終わった後は習い事や課外活動が増えてきて…そんなスケジュール中心ですね。ただ、少し時間ができた時には一緒に遊ぶこともあります。休日は、下の子がいない時にお兄ちゃんが興味を持ちそうなことを一緒にやってみたり、彼が行きたいところに連れて行ったりしています。祖母の家に行くと、みんなでトランプやオセロ、双六、かるたなどのボードゲームをよくします。最近は彼が双六に目覚めていて、楽しそうに遊んでいますね。
あとは家では本を読むことが多いです。本が大好きで自分で静かに読んでいますね。家にはたくさんの本を並べておいて、いつでも取り出せるようにしているので、私が何かを教えるよりも、本を通じて自分で学んでくれています。「ママ、こんな風にするといいよ」って自分から教えてくれることもありますね。最近読んでいる本でいうと、科学の本シリーズです。「ふわふわ」「チクチク」といった感覚的なテーマの本とか、決まり事や豆知識を学べる本も好きみたいです。自然と知識が増える内容のものに興味を持っています。 - 普段お子様はご自宅や園でどんな遊びをして過ごすことが多いですか?また、好きですか?
- うちの子は毎日日記を書いています。というのも、私が一緒にいられないことが多いので「園で何してるのかな?」って私自身が知りたくて、日記を書くようにお願いしているんです。その日記を読むと、「砂遊び」と「ブロック遊び」という言葉がよく出てくるので、園や家でも積み木やブロックを楽しんでいるのかなと思います。
- 現代は様々な教育法や習い事が存在しますが、そんな中なぜ「積み木」という玩具に対して重要性を感じましたか?
- いま私が平日に連れて行っている習い事って、ほとんどが答えを導き出すことを求められるものばかりなんです。例えば、「先生がやっている通りに弾く」とか、「みんなで一つの正解を目指す」とか。そういう習い事ももちろん大事だとは思いますが、積み木はその真逆の存在だと感じています。積み木には決まった正解がなくて、自分で考えたり自由に発想を広げたりできるんですよね。だからこそ、親にとってもこどもにとっても特別な意味があるんだと思います。
- 積み木は本来こどもから大人まで誰にとっても楽しめる遊びです。ところが、積み木に全くなじめず、楽しめない方もいます。それはなぜだと思いますか?
- 遊び方を知らないからじゃないでしょうか。私自身もそうでしたが、積み木で遊びながら育ったわけではないので、最初は「息子に教えるなんて無理だな」と思っていました。でも、お教室で先生方がいろいろと遊び方を導いてくださったり、サポートしてくださる姿を見たりしていて「あ、これなら私も一緒に楽しめそう」と感じたんです。まだまだ積み木初心者なので上手く説明できるわけではないんですが、先生方のおかげで自分も自然に楽しめるようになってきたと思います。
- あなたが思う、理想的な子育てや教育とはなんですか? その実現は簡単ですか、難しいですか?
- 私が理想的だと思うのは、特に3歳までの間にできるだけ多くのインプットをすることですね。3歳までに視野を広げたり、様々な経験を通じて成長の土台を作ることが大切かなと考えています。例えば旅行に連れて行ったりとか、色々な遊びやイベントに参加したりすることで、まだ狭い子どもの世界を広げることができるのかなって。あとは座学のような要素も取り入れて、カード遊びをしたり本を読んだりしました。実際に、2歳7か月の頃には1万冊の本を読み聞かせしました。それがきっかけでうちの子は本好きになりました。私としては、子どもに言葉や知識をインプットするために、できる限りのことをしてきたと思います。でも、これを「簡単」と言えるかどうかは分かりません。親が考えられる範囲のことを全力で取り組む必要があるので、やっぱり努力は必要ですね。
- 茉依子さんの「自分の信じたことや決めたことをしっかりやり抜こう」という精神はどこから培われたのですか?
- うーん、なんでしょうね。正直、自分でもよく分かりません。ただ、私は育児書とかはあまり読まないんです。もし読むことがあっても、目次を見て気になるところだけを読む程度ですね。「この人はこう思ってるんだな」くらいの感覚で捉えています。
あと、例えば幼児教室とかも、多くの方が通われますよね。私も行ってみたことはあるんです。でも、「これなら自分でもできる」って思ってしまって(笑)。大金を払うくらいなら、自分でやったほうがいいと思いました。その頃は仕事をしていなかったので、この子のために10分でも時間を使おうと決めて、全力で時間を活用しました。
そういう意味では、情報にただ流されたり、言われるがままに行動したりするのではなくて、自分の目で確かめて「これは必要」「これは不要」と取捨選択する力が自然と身についたのかもしれません。自分の軸を大切にして、この子に合った方法を考えてきたと思います。
例えば、この子の性格に合うやり方を試行錯誤して、「こうすれば受け入れてくれるかな」「これはダメなのかな」と、実際にいろいろ試しながら進めてきました。自分で考えて、自分なりに決めて行動する。そんなふうに子育てをしてきたからこそ、今の私があるのかなと思います。 - 積み木の難しい所は、初めから楽しいものやすぐに遊べる状態に完成されておらず、「自分たちでまず作ってから遊ぶ。何を作るか?も考える」という過程が必要です。この少し大変だったり手間だったりする高度な遊びを取り入れて育つと、大人になった時に、どんなことに役立ちそうですか? また、大人自身もこの環境で遊ぶことでどんないいことがありそうですか?
- 積み木を通して育つことで、将来リーダーシップを取れるようになったり、周りの状況を見て自分の意見をしっかり持てるようになると思います。さらに、諦めない心や集中力も身に付くと思います。空間認知能力なども養われると言われていますが、精神面での成長も大きいと感じています。
大人も、この環境で遊ぶことで得られるものはたくさんあると思います。例えば、普段は子どもと一緒に遊べない私でも、こうした場では先生と一緒に協力して何かを作り上げることができ、そこから新たな発想やアイディアを得ることができます。主人も積み木で楽しんでいたので、ちょっと童心に帰ったような感覚で、自分も結構出来るんじゃないかな?と思ったりしてますね。積み木の数がたくさんあるから、色々な形を作ってみることができ、遊びながら自分の可能性を広げられると思っています。 - これから横浜つみきに体験に来てみたいと思っている方へひとことお願いいたします。
- そうですね、積み木って本当に素晴らしいと思います。積み木には正解がないんです。だから、何を作ってもいいし、それを認めてもらえて褒めてもらえる。それって子どもの新たな可能性を見つけるきっかけになるんじゃないかなと思うんです。私自身も、子どもが積み木を通してどんどん成長していく姿を見て、ずっと支え続けていきたいという気持ちになりました。だから、もし迷っている方がいたら「一緒に行ってみようよ!」と声をかけたいです。親子で楽しい体験ができるはずです。